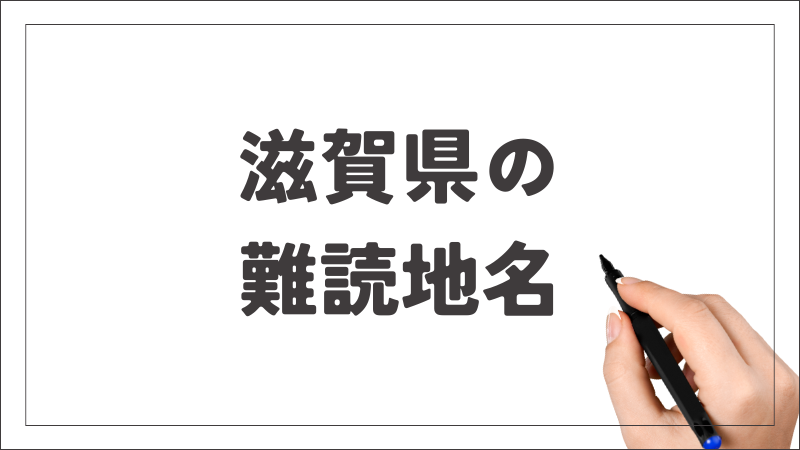滋賀県といえば琵琶湖や歴史ある城下町で有名ですが、実は「読めたら天才!」と話題になる難読地名の宝庫でもあります。
初めて見ると「え、これなんて読むの?」とつい声に出してしまいそうな地名ばかり。
今回の記事では、滋賀県の難読地名を20個厳選してご紹介します。
地名にまつわる歴史や由来も少しだけ解説するので、ちょっとした雑学としても楽しんでくださいね。
さて、いくつ読めるかチャレンジしてみましょう!
関連記事
こちらもCHECK!
目次
穴太(大津市)
パッと見「あなふと」と読んでしまいそうなこの地名。
正解はあのうと読みます。
穴太は大津市に位置し、周辺には自然豊かな風景が広がります。この地名は古代日本語の地形用語に由来しているとされ、歴史的にも興味深い地域です。意外とシンプルな読み方ですが、漢字の並びに惑わされてしまいがち。近くには穴太寺という寺もあり、散策にはぴったりのエリアです。
膳所(大津市)
一瞬「ぜんしょ」と読みたくなるこちらの地名。
正解はぜぜです。
膳所は琵琶湖沿いの大津市にあり、歴史的な背景を持つ地域。膳所城があった場所としても知られています。この読み方は、古代からの地名の音韻が変わらず使われているためで、地元の人にとっては馴染みのある名称です。ただし、他県から訪れる方はまず読めないかもしれませんね。
和邇(大津市)
ヒントはクロコで有名なあの動物。
その通り、わにと読みます。
和邇は大津市の北部に位置する地域で、古くから人々が生活してきた土地です。名前の由来については諸説ありますが、古代の地名に関連している可能性が高いとされています。近くには琵琶湖があり、アウトドア好きにはたまらないエリアです。
男鬼(彦根市)
「男鬼」、これを「おとこおに」と読んでしまいませんか?
正解はおおりと読みます。
彦根市にあるこの地名は、険しい山々に囲まれた地域として知られています。「鬼」という文字が使われているため、少し怖いイメージを抱きがちですが、実際はのどかな風景が広がっています。この名前には、山岳信仰や伝説が影響しているとも言われています。今は廃村になっています。
楡(彦根市)
一見「にゅう」かな?と思いませんか?
実はにれと読みます。
楡は彦根市の歴史ある地域で、その名の通り、昔は楡の木が多く見られたことに由来しています。この地名はシンプルながら、現代ではあまり使われない漢字が使われているため、初見ではなかなか読みにくいかもしれません。
阿閉(長浜市)
「阿閉」、ぱっと見では「あへ」と読んでしまいそうです。
しかし正解はあつじと読みます。
長浜市にあるこの地名は、古代から続く地名のひとつ。阿閉氏という豪族がこの地を治めていたことが名前の由来とされています。歴史的な背景を感じさせる地名で、周辺には古墳や神社が点在しています。
主計(長浜市)
「主計」、初見では「しゅけい」と読んでしまいそうですね。
正解はかずえと読みます。
長浜市に位置するこの地域は、歴史ある町並みが残るエリア。名前の由来は定かではありませんが、古くからこの地域で使われてきた地名です。地元の人々には馴染みがありますが、観光で訪れる方には難読地名としてインパクトがあります。
渡岸寺(長浜市)
「渡岸寺」、これは「とがんじ」と読みたくなりませんか?
実はどうがんじと読みます。
長浜市にあるこの地名は、国宝の十一面観音像が安置されている渡岸寺観音堂で知られています。仏教の影響を受けた地名で、歴史的・文化的価値が高い地域です。
赤尾町(近江八幡市)
「赤尾町」、これは「あかおちょう」と読みたくなりそうですね。
正解はあこうちょうと読みます。
近江八幡市に位置するこの地名は、江戸時代から続く歴史ある地名のひとつです。赤い尾を持つ鳥に由来しているという説もありますが、正確な由来は未だ謎に包まれています。周辺には豊かな田園風景が広がり、観光客にも人気のエリアです。
千僧供町(近江八幡市)
こちらの「千僧供町」、初見では「せんそうきょうちょう」と読んでしまいそうです。
正解はせんぞくちょうです。
この地名は、かつて多くの僧侶が集まり法要が行われていたことに由来しているとされています。近江八幡市の歴史的なエリアで、昔ながらの町並みも残されています。読み方の難しさだけでなく、背景にある歴史も興味深いですね。
下物町(草津市)
「下物町」、これは「しもものちょう」と読んでしまいがちです。
正解はおろしもちょうと読みます。
草津市にあるこの地名は、古代から続く地名で、特に琵琶湖に近いエリアとして知られています。この地名は、土地の形状や古い地名に由来していると言われています。初見では読みにくいですが、現地では親しまれている名称です。
矢橋町(草津市)
「矢橋町」、ぱっと見では「やばしちょう」と読みたくなりそうですね。
正解はやばせちょうです。
草津市にあるこの地名は、かつて矢橋港が琵琶湖の交通拠点として栄えたことに由来しています。港町としての歴史を持つエリアで、現在もその名残を感じられるスポットが多くあります。観光地としても注目されています。
金勝(栗東市)
「金勝」、つい「かなかつ」と読んでしまいそうなこの地名。
正解はこんぜです。
栗東市に位置するこの地名は、周辺にある「金勝山」に由来しています。このエリアは豊かな自然が広がる地域で、ハイキングコースとしても人気があります。名前の由来には、金を得る勝利を祈願する意味が込められていたとも言われています。
鈎(栗東市)
「鈎」、これを「かぎ」と読むのは早計です。
正解はまがりと読みます。
栗東市にあるこの地名は、かつて道が大きく曲がっていた場所に由来していると言われています。読み方も特徴的ですが、地元では当たり前に使われているため、観光客には驚きの地名となっています。
貴生川(甲賀市)
「貴生川」、つい「きせいがわ」と読んでしまいがちですね。
正解はきぶかわと読みます。
甲賀市にあるこの地名は、鉄道の駅名としても知られています。歴史的な背景としては、古代から続く地名で、地域の中心地として発展してきた場所です。滋賀県内を移動する際には耳にすることが多い地名ですが、初見で読める人は少ないでしょう。
杣中(甲賀市)
「杣中」、これは「そまちゅう」と読んでしまいがちです。
正解はそまなかと読みます。
甲賀市のこの地名は、かつて木材の産地であったことが由来とされています。「杣」という文字自体が古語として珍しいため、現代ではあまり見かけない地名です。自然豊かなエリアで、甲賀市の伝統を感じることができます。
饗庭(高島市)
「饗庭」、初見では「きょうば」と読んでしまいそうです。
正解はあいばです。
高島市にあるこの地名は、古代の豪族や神事に関係する言葉に由来しています。現在では自然豊かな風景が広がり、観光地としても注目されています。この地名には、古代日本の文化や歴史が色濃く反映されています。
安曇川(高島市)
「安曇川」、これは「やすくもがわ」と読んでしまいがちですね。
正解はあどがわと読みます。
高島市に位置するこの地名は、安曇族という古代の民族が由来と言われています。安曇川は琵琶湖に注ぐ川としても有名で、自然豊かな地域です。アウトドアや釣りを楽しむには最適の場所で、観光客にも人気があります。
顔戸(米原市)
「顔戸」、これは「かおど」と読んでしまいそうですが…
正解はごうどです。
米原市にあるこの地名は、古代の地形や集落に由来していると言われています。現在も田園風景が広がるのどかな地域で、歴史の名残を感じられるスポットです。地名の響きもユニークで、地元の人に親しまれています。
山女原(甲賀市)
最後は「山女原」。これは「やまめはら」と読んでしまいそうですね。
正解はあけびはらです。
甲賀市に位置するこの地名は、自然豊かな地域で、かつて山女(やまめ)が多く生息していたことに由来するとも言われています。漢字の見た目に惑わされやすい地名ですが、その由来を知ると納得できますね。
まとめ:滋賀県の難読地名
以上、滋賀県の難読地名20選をご紹介しました!
いくつ読めましたか?
これらの地名は、それぞれに地域の歴史や文化が色濃く反映されています。
旅先でこうした地名を知っていると、地元の人との会話も弾むかもしれませんね。
次回、滋賀県を訪れる際には、ぜひこの記事を参考に、難読地名巡りを楽しんでみてください!
関連記事
こちらもCHECK!