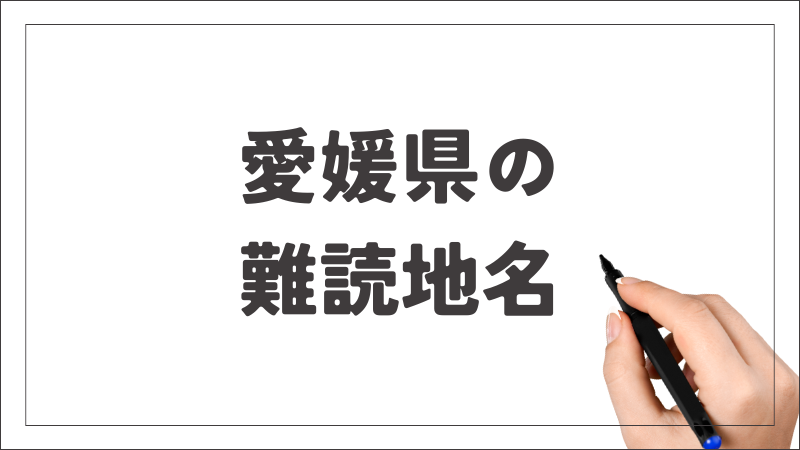愛媛って読みムズ地名の宝庫なんですよ。
たとえば「浅海原」――パッと見で読めました?
県庁所在地の松山はもちろん、今治・西条・伊予・上島町までクセ強な字面が勢ぞろい。
地元民なら常識でも、県外勢はまずつまずくはず。
今回は正式な住居表示にあるガチ実在の難読地名だけを20個に厳選。
由来や背景もつまみ食いしつつ、クイズ感覚でサクッとどうぞ!
関連記事
目次
浅海原(松山市)
最初の一撃から強烈。読みを分けるのは「海」の一文字…ここで大体つまずきます。
実は「あさなみはら」と読みます。
松山市北東部、「浅海(あさなみ)」エリアに由来する地名です。瀬戸内の穏やかな浅い海を思わせる古い呼称が土地の名として残りました。同じ「浅海」でも「あさみ」や「せんかい」とは読まず、地域固有の読みが堅持されているのがポイント。住所表記として今も現役なので、郵便物やカーナビ設定で読み違えると目的地検索に手間取る典型パターンです。
太山寺町(松山市)
「たいさんじ」までは読めても、最後の一字で「ちょう?まち?」と迷いがち。
正しくは「たいさんじまち」と読みます。
国の重要文化財で名高い「太山寺」を中核とする一帯に由来。町名の読みは“まち”固定で、行政・郵便の正式読みでも一貫しています。寺社ゆかりの地名は全国にありますが、読みが地域流儀で固定されるのが常。観光案内の表記ゆれ(カタカナや英字)に惑わされず、住所は“太山寺町”で覚えておくと迷いません。
会津町(松山市)
「あいづ?会津って福島?」と脳内が一瞬北へワープしがち。
そのまま「あいづまち」と読みます。
松山城下の町割り由来の小字が重なって残ったタイプの地名。全国的に知名度の高い会津と同字ですが、ここは愛媛・松山の会津町。地名は同字でも読みや背景は地域別、という良い例です。ナビ検索で県名を付け忘れると東北に飛ぶあるあるが起きるので要注意。
上市(松山市)
直球に見えて読みを外しやすい、「うえいち」派も一定数います。
読みは「かみいち」です。
「上(かみ)/下(しも)」の上下区分は旧来の川上・川下や本家・分家の位置関係を示す日本的地名の王道。松山の上市も“かみ”読みで定着しています。近隣に似た字面がある場合、宅配やタクシーの口頭指示はカタカナ読み+市区名を添えると誤配防止に役立ちます。
保免上(松山市)
まず「保免」を“ほめん”と読めるかが第一関門。
正解は「ほめんかみ」と読みます。
松山市南部の「保免」エリアは、保免上・保免中・保免西などの小区分が並ぶ住所体系。“上(かみ)”はエリア内の相対位置を示します。「保険」や「保免(運転免許の略)」と取り違えられがちですが、地名としては固有の語。宛名書きでは“免”の字を崩さないのがコツです。
久万ノ台(松山市)
中黒ではなく「ノ」。この小さな一文字が地名っぽさを爆上げさせます。
「くまのだい」と読みます。
旧久万街道方面へ向かう台地縁を示す呼称とされ、“ノ”入りの表記は公的住所でも採用。「くま」は“熊”ではなく“久万”である点に注意。固有名詞としての“ノ”は読み方の一部なので、履歴書や契約書の住所欄でも省略せず正確に記すのがベターです。
味酒町(松山市)
お酒好きの人ほど「みさけ?みしゅ?」と迷う不思議トラップ。
答えは「みさけまち」です。
松山城下の古い町名のひとつ。味酒(みさけ)は神前に供える酒=御酒(みさけ)に由来する説が有力で、古語的な響きが残ります。「味酒神社」など周辺の社名・施設名にも読みが波及。グルメ記事で「あじざけ」と誤記されがちなので要注意。
粟井河原(松山市)
まず「粟井」を“あわい”で取れるかどうか。ここで半分勝負が決まります。
読みは「あわいがわら」です。
「河原(かわら)」は地名で“がわら”と濁るケースが多く、ここも連濁が起こる典型。中世の荘園名や小字が積み重なって成立した地名群の一角で、現行の住居表示でも使用中。似た表記の「粟石」「粟井谷」と混同しやすいので、番地まで正確にセットで覚えたい地名です。
土居田町(松山市)
読めそうで読める系。「どいでんちょう」と誤爆する人もいます。
正しくは「どいだまち」です。
「土居」は城郭や館(やかた)に由来する語で全国各地に残ります。松山の土居田は“田”が付くことで開発・耕地の広がりを示し、現在は幹線道路や伊予鉄沿線の生活拠点に。駅名やバス停名と地名表記が微妙に違う場合があるため、ルート検索時は“町”の有無に注意を。
苞木(松山市)
一画ごとに初見殺し。「包木」「胞木」あたりに誤変換されがち。
読みは「すぼき」です。
「苞(つと・ほう)」は植物のつぼみを包む葉を指す字で、地名では“すぼ”と読む例が点在。松山市の苞木は古い小字が現行住所に残ったタイプで、全国的にもレアな読み。地名辞典・地番図でも確認できる実在の住所なので、漢字入力時は“すぼき→苞木”の辞書登録が作業効率アップの近道です。
桑村(西条市)
「くわむら?村がそのまま読めるの怖い」と身構えるけど実は素直。
そのまま「くわむら」と読みます。
西条市域の旧郡名・旧村名に由来する大字で、現住所にも生きています。養蚕と桑の栽培史が地名に刻まれ、地理史の教科書を素で体現。村が付く現行住所は珍しく感じますが、四国・中四国ではまだ見られるパターン。郵便番号検索でもヒットする現役です。
石鎚町石鎚(西条市)
同じ語が二連。つい「いしづちまち・いしづち?」と読み分けに迷うやつ。
「いしづちちょういしづち」と読みます。
霊峰・石鎚山を戴く西条市ならではの地名構成。「石鎚町」という大きな町域の中の「石鎚」地区を指すため、町名+字名が同字になるスタイルです。住居表示・地番上の正式表記で、カーナビは後段の“石鎚”まで入れないと別所に飛ぶことがあるので注意。
旦之上(今治市)
最難関の部類。これで「たんのうえ」と読んだ人、惜しい!
正解は「あさのうえ」です。
「旦」は“あした・あさ”の意味を持つ漢字。地形や方角(朝日が先に当たる高まり等)に由来した地名とされます。今治市域には古い小字が現住所へ継承された例が多く、読みは伝統どおり“あさ”。地名は常用音訓に縛られない――を体感できる好例です。
古谷(今治市)
これは「ふるたに」派と「こや」派に割れがち。
ここは「こだに」と読みます。
四国の山間地で見かける“古谷(こだに)”読み。谷筋の開発史や旧家の屋号に結び付くケースも。今治市は島嶼部・山間部が入り組むため、同字異読の典型が点在します。表札やバス停のローマ字表記で“Kodani”を見つけたら、この読みだと確信してOK。
小網町(今治市)
小さな「網」で「こあみ」と読ませたいところを、地名はひとひねり。
読みは「こうみちょう」です。
小網(こうみ)は古語読みに近い音便。城下町の町割りに由来する“町(ちょう)”が付いて現行住所に。今治城下の町名は読みが独特なものが多く、歴史散歩のルート作成で地名読みを押さえておくと、古地図との照合が捗ります。
高井神(越智郡上島町)
島名で聞いたことある人は多いはず。濁る?濁らない?で揉めがち。
正しくは「たかいかみ」と読みます。
上島町の離島「高井神島(たかいかみじま)」の島名に通じる地名。“神(かみ)”が“がみ”に濁らないのが地域の正式読みです。島嶼部の住所は「○○島○○」のように字面が長くなるため、宅配の宛先では番地まで丁寧に。フェリー時刻検索でも島名の正式読みが鍵になります。
明神(大洲市)
地名あるあるの神社系ワード。読みは統一っぽく見えて実は地域差も。
ここは「みょうじん」です。
大洲市内の社叢や祠に由来する小字・字名由来。全国で“みょうじん/みよし”など読みに揺れがありますが、当地は“みょうじん”で定着。観光ポスター等の振り仮名もこの読みで出ることが多いので、旅の予習にも役立ちます。
喜多灘(伊予市)
海っぽさ満点の字面。読みはストレートにいけるでしょうか?
答えは「きたなだ」です。
瀬戸内の灘(外海に面した海域)を指す語が入り、伊予灘の景観を想起させる地名。喜多郡の歴史とも関係が深く、鉄道駅名・バス停にも用例あり。観光写真のキャプションで“北灘”と誤字されがちですが、住所は必ず“喜多灘”。表記ブレに注意です。
波止浜(今治市)
港町感たっぷり。つい「はしはま」と読みたくなる人、多数。
正解は「はとはま」です。
波止(はと)は船着き場・防波堤を意味する語で、瀬戸内の港町に広く残る古い表現。今治の波止浜は造船・物流の要衝として発展してきました。駅名・港名・工業地帯名に広く使われるため、住所入力時に“波止”を“波戸”“鳩”と誤変換しないように要チェック。
延喜(西条市)
元号っぽいこの字面、つい歴史の授業を思い出しますよね。
読みは「えんぎ」です。
地名に元号が残るパターン。社寺縁起や年号奉名に由来する説が伝わります。西条市内では住所として現役で、農地や集落の小字としても機能。読みは“えんぎ”固定なので、企業の所在地表記でも振り仮名を付けると問い合わせ対応がスムーズになります。
まとめ:愛媛県の難読地名、あなたはいくつ読めた?
20連発、おつかれさまでした!
愛媛は城下町の町割り、瀬戸内の海語、社寺ゆかりの古語――いろんな由来がミックスして読みのクセが生まれています。
旅行のルート決めや物件検索、郵便の宛名書きでも役立つ知識なので、気になる地名はブックマーク推奨。
次はどの県に挑戦しましょう?この地名も入れて!のリクエストもお待ちしてます。
関連記事