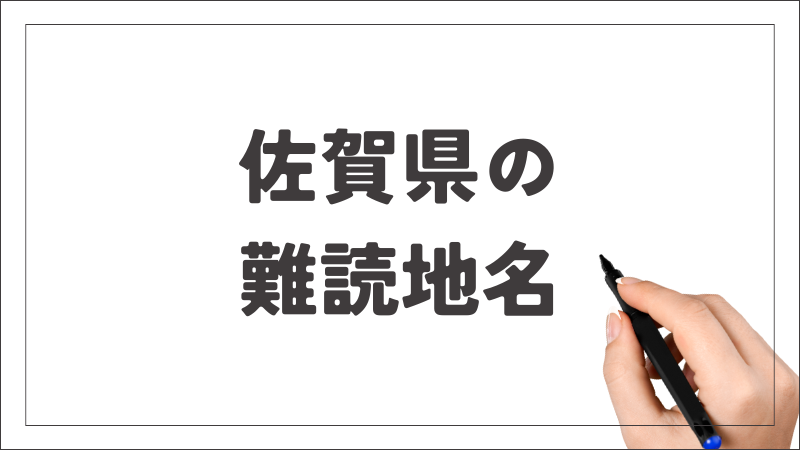いきなりですが、クイズです!
「咾分」って、これどう読むか分かりますか?
「らいぶん」?「しょうぶん」?
うーん、惜しいけどハズレ!
実は、佐賀県にはこうした「読めそうで読めない」クセつよ地名がゴロゴロあるんです。
地元の人には当たり前でも、初見で読めたらもう天才クラス!
今回は、そんな佐賀県の難読地名を20個ピックアップしてご紹介。
答えはもちろん、ちょっとした歴史や由来も添えて解説していきます。
さて、あなたはいくつ読めるかな?
クイズ感覚で最後までお楽しみください!
関連記事
目次
箞木(唐津市厳木町)
これ、なんとなく「ふでぎ」って読んじゃいそうな雰囲気ありませんか?
正解は「うつぼぎ」です。
箞木は唐津市の山間部にあるエリア。古くから農業が盛んな地域で、自然豊かな風景が広がっています。「箞」は竹製の道具を意味する漢字で、地元の生活と関係があるのかもしれません。読み方は代々地域に受け継がれてきた独自のものです。
納所(多久市)
「のうしょ」や「おさめどころ」って読みたくなっちゃいますよね。
実は「のうそ」と読みます。
多久市にある納所は、かつて神社への供え物を納める場所だったという説もあります。現在では住宅地として静かな環境が整っており、地域の人にとっては馴染み深い名前ですが、県外の人からすると「???」となりやすい地名です。
馬渡島(唐津市)
パッと見、「うまわたりじま」でしょって思いますよね?
でもこれ、「まだらしま」なんです!
唐津市の沖合に浮かぶ有人島で、美しい海と自然に囲まれたスポット。釣りやダイビング好きにはたまらない場所です。「馬渡」と書いて「まだら」と読むのは珍しく、方言や音の変化が影響していると考えられています。
石動(吉野ヶ里町)
「いするぎ」かな?富山の地名と同じ読みかも?
佐賀では「いしなり」と読みます。
吉野ヶ里町にある石動は、古代の遺跡が多く発見されているエリアに近く、歴史的な背景が感じられる地域です。「石が動く」なんて意味深な漢字ですが、読み方はまったく想像つかないですよね。
養母田(唐津市)
「ようぼた」っぽく見えますが、これもひっかけです。
正しくは「やぶた」と読みます。
養母田は唐津市の農村地帯に位置しており、静かな田園風景が広がります。「やぶ」は雑木林や境界を表す古語、「た」は田んぼを意味しているとも言われており、まさに自然と暮らしが密接な地域の象徴といえる地名です。
外津(玄海町)
「そとづ」や「がいしん」って読んじゃいそうなこの漢字。
答えは「ほかわづ」です。
外津は玄海町の沿岸部にあり、海の香り漂う漁業の町です。「外にある津(港)」という意味で名づけられたと考えられますが、読みはかなり独特。地元の人には普通でも、観光客は間違いなく読めないランキング上位です。
作出(佐賀市東与賀町)
これは「さくしゅつ」とか言いそうですよね。
でも読み方は「つくいで」です。
佐賀市東与賀町にあるこの地名は、干拓地として栄えた地域のひとつ。湿地帯を開拓してできた土地という背景があり、「作り出す」=「つくいで」になったとする説もあります。土地の歴史を感じられる味のある地名です。
神田内田(唐津市)
漢字だけ見ると、「かんだうちだ」ってそのまま読んじゃいそう。
正解は「こうだうちだ」です。
唐津市にある地名で、もともとは「神田(こうだ)」と「内田(うちだ)」という二つのエリアが統合された可能性もあります。読み方は難しくないけど、最初はほぼ100%間違えられるタイプの地名ですね。
亀頭六(嬉野市)
「かめあたまろく」…まさかね?
なんと「きつろく」と読みます!
嬉野市にあるこの地名は、その字面のインパクトが強烈すぎて、読み方より先に突っ込みたくなります。「亀頭」は山の形状や地形に由来するという説もあり、地元では普通に使われている歴とした行政地名です。
莞牟田(神埼市神埼町)
この漢字、「かんむた」「かんぼうだ」…いろいろ想像しちゃいます。
でも正しくは「くぐむた」と読みます。
神埼市の神埼町にある地名で、古い読み方がそのまま残っています。音の響きに方言的な要素があり、由来ははっきりしていませんが、地元では昔から親しまれてきた呼び名です。
大良(唐津市)
これ、「おおよし」「たいりょう」って読んじゃいません?
実は「だいら」です。
大良は唐津市の郊外にあり、田園風景が広がるのどかなエリア。「良い土地が広がる場所」という意味合いも含まれていたとされ、読み方も地形に合った穏やかな響きが特徴です。
犬王袋(鹿島市)
なんとなく「けんおうぶくろ」とか言いたくなっちゃうこの地名。
実は「いのうふくろ」と読みます。
鹿島市の山あいにあるエリアで、「犬王」は古代の人物名や伝承に登場する名残とも言われています。漢字のインパクトが強い割に、読み方はやさしめ。だけど初見ではやっぱり読めません!
咾分(佐賀市)
「らいぶん」「しょうぶん」…正解はどっち?
どっちでもなく「おとなぶん」です!
佐賀市に存在する実在の住所で、漢字のクセがとにかくすごい。「咾」は古字で「音を返す」などの意味があると言われていますが、現代ではなかなか見かけません。読めたらマジでスゴいです。
水主(唐津市)
これ「すいしゅ」「みずぬし」って読んでませんか?
正解は「かこ」です。
唐津市にある海沿いの地名で、古くは船の「水主(かこ)」が住んでいた場所だったと言われています。港町らしい歴史が感じられるこの地名、由来を知ると読み方に納得できますね。
八谷搦(伊万里市)
漢字の並びだけで難読認定しちゃいそうなこの地名。
実は「はちやがらみ」と読みます。
伊万里市にある八谷搦は、かつて水路や干潟が入り組んでいたエリアです。「搦」は「入り組んだ入り江」などを意味する古語で、水辺地帯の地名によく見られます。難読漢字×方言の最強タッグです。
三本槲(佐賀市)
「さんぼんかしわ」って読みたくなりますよね。
でもこれは「さんぼんがしわ」と読みます。
佐賀市の住宅地にある地名で、「槲(がしわ)」はブナ科の樹木を指します。地元では「がしわ餅」にも使われる葉っぱとしておなじみ。木にちなんだ自然豊かな印象のある地名です。
杠(佐賀市)
この漢字、そもそも読める人いるんでしょうか?
正解は「ゆずりは」です。
佐賀市にある地名で、「杠」はユズリハの木を意味する漢字。お正月飾りにも使われる縁起の良い植物で、古くから日本人に親しまれています。読みは美しいけれど、漢字はかなりマニアックです。
莇原(多久市)
「そうげんばら」でも「ざんばら」でもありません。
正解は「あざみばる」です。
多久市にあるこの地名、「莇(あざみ)」はトゲのある植物、「原(ばる)」は野原を意味する九州特有の言い回しです。野生のアザミが群生していたことにちなんでつけられた説もあります。
咾搦(白石町)
また出てきました「咾」の字!
こちらは「おとながらみ」と読みます。
白石町にある地名で、先ほどの「咾分」と同じく「咾」を使った珍しい地名です。「搦」は入り江や湿地帯の象徴で、干潟だった名残を示しているのかもしれません。音の響きが独特です。
廿治(白石町)
これは「にじゅうじ」「とおやす」じゃないんです。
読み方は「はたち」です!
白石町の実在する住所で、「廿(はたち)」は古くから「20」の意味を持つ漢字です。成人を意味する言葉にも通じるこの地名、意外と縁起が良いかもしれません。
まとめ|佐賀県の難読地名はクセが強い!
いかがでしたか?
佐賀県には、見たことあるような漢字でも意外すぎる読み方の地名がたくさん存在します。
地元の人にとっては当たり前でも、初見の人にはなかなか読み切れないものばかり。
今回紹介した20の地名、あなたはいくつ読めましたか?
旅行や引っ越し、地元トークのネタとしても、覚えておくと話のタネになること間違いなし!
気になった地名があれば、実際に訪れてみるのも面白いですよ♪
関連記事