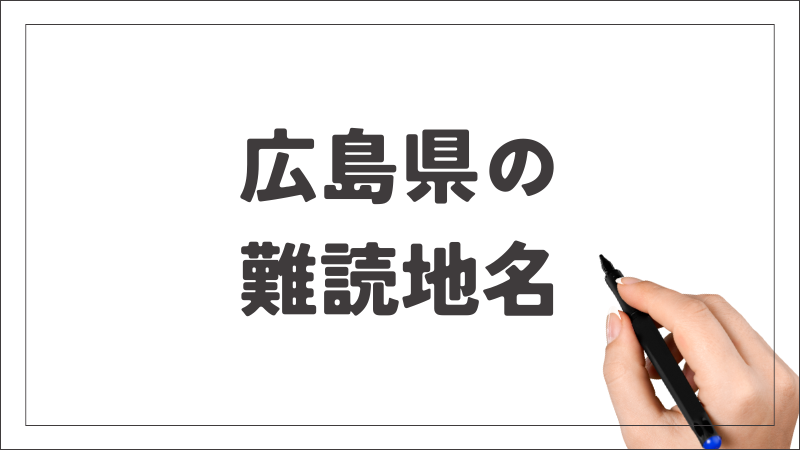いきなりですが、クイズです!
「温品」
これ、何と読むか分かりますか?
「おんひん?」「あたたかしな?」 いやいや、そんな単純な読み方じゃないんです。
正解は…ぬくしな!
広島県民でもなかなか読めない地名が、実はまだまだたくさんあるんです!
広島といえば、お好み焼きや原爆ドーム、宮島の厳島神社が有名ですが、地名の難易度もなかなかのもの。
初見で読める人は、かなりのツウかもしれません。
この記事では、広島県内の「読めたら天才」レベルの難読地名を18個ピックアップして紹介します。
クイズ感覚で楽しんでみてくださいね!
それでは、早速いってみましょう!
関連記事
目次
銀山町(広島市中区)
「銀山」と書いて、「ぎんざん?」それとも「ぎんやま?」
実はかなやまちょうと読みます!
江戸時代、広島藩の銀山があったことが由来とされています。現在は広島市中心部にある繁華街で、飲食店やバーが立ち並ぶエリアとして賑わっています。観光客が多く訪れる場所ですが、この地名を正しく読める人は意外と少ないかも?
上幟町(広島市中区)
「幟」ってそもそも何て読むの?と戸惑う人も多いはず。
正解はかみのぼりちょう!
「幟(のぼり)」は、戦国時代の旗印として使われていたもの。昔、この地域には武家屋敷が多く、幟を掲げた家もあったことから名付けられたと言われています。現在は閑静な住宅街で、おしゃれなカフェも点在していますよ。
薬研堀(広島市中区)
「薬」と「研」が並ぶと、何かの研究所みたいですよね?
でも実はやげんぼりと読みます!
広島市の歓楽街として有名なエリアですが、名前の由来は意外にも江戸時代に遡ります。「薬研」は漢方薬を作るための道具で、昔このあたりに薬屋があったことから名付けられたと言われています。
温品(広島市東区)
「温かい品」って書くと、なんだかほっこりしそうな名前ですが…
実はぬくしなと読みます!
地名の由来は諸説ありますが、古くから温泉が湧いていたとか、暖かい土地柄だったことから名付けられたとも言われています。初見で読めたらすごい!
阿品(廿日市市)
「阿品」って「ありな?」それとも「おしな?」
正解はあじな!
広島県廿日市市にある地名で、JR「阿品駅」や広電「阿品東駅」もあります。由来には諸説あり、「阿(あ)」は古語で「神聖な場所」を意味し、「品(しな)」は土地を指すとも言われています。宮島が近いため、歴史的にも深い意味を持つ地名かもしれませんね。
加計(山県郡安芸太田町)
「加計」、これは「かけい?」
正解はかけ!
山県郡安芸太田町にあるこの地名は、自然豊かなエリアとして知られています。かつては「加計町」として独立した自治体でしたが、2004年に安芸太田町として合併しました。地名の由来は定かではありませんが、山間部にあるため、「崖(がけ)」が転じて「かけ」になったという説もあります。
御調町(尾道市)
「御調町」って「ごちょうちょう?」
実はみつぎちょう!
尾道市にあるこの地名は、かつて「御調郡(みつぎぐん)」と呼ばれていたことに由来します。「調(つぎ)」は、古代の税として納められていた品物のことを指し、重要な産業拠点だったことがうかがえます。現在はのどかな田園風景が広がる地域です。
因島(尾道市)
「因島」は「いんとう?」「いんじま?」
正解はいんのしま!
瀬戸内海に浮かぶ島の一つで、造船業が盛んなことで有名です。かつては「因島市」でしたが、2006年に尾道市と合併しました。戦国時代には村上水軍の拠点としても知られ、歴史ロマンあふれる場所です。
忠海(竹原市)
「忠海」、これは「ちゅうかい?」
正しくはただのうみ!
竹原市にある港町で、大久野島(ウサギ島)へのフェリーが発着する場所としても有名です。「忠」の字は「誠実さ」や「忠義」を意味し、「海」と組み合わせて名付けられたと考えられています。
吉舎町(三次市)
「吉舎町」って「よしやちょう?」
実はきさちょう!
三次市にあるこの地名は、古くから宿場町として栄えていた歴史を持っています。由来には諸説あり、「吉(き)」は「縁起の良い地」、そして「舎(さ)」は「集落」を意味するとも。初見で読める人は少ないかも?
土生町(尾道市因島)
「土生町」って「どしょうちょう?」
正解ははぶちょう!
因島にある地名で、港町として栄えてきた地域です。地名の由来は、「生(ぶ)」という音が古くから使われていたことが影響しているとも言われています。現在は観光地としても人気があります。
斎島(呉市)
「斎島」、これは「さいじま?」
正しくはいつきしま!
呉市にあるこの島の名前は、「斎(いつき)」という言葉が「神聖なものを清める場所」を意味することに由来しています。かつては神に仕える人々が住んでいたと言われ、神秘的な雰囲気が漂う場所です。
水分峡(安芸郡府中町)
「水分峡」、これって「みずぶんきょう?」
正解はみくまりきょう!
「水分(みくまり)」は、古くから水源や水を分配する場所を指す言葉。この地域には豊かな自然が広がり、ハイキングコースとしても人気のエリアです。名前の響きも独特で、初見ではなかなか読めませんよね。
坪生(福山市)
「坪生」って「つぼい?」
実はつぼう!
福山市にある地名で、田園風景が広がるのどかな地域です。地元の人には馴染みのある読み方ですが、県外の人には難読地名として知られています。
久井(三原市)
「久井」、これも「きゅうい?」「ひさい?」
正解はくい!
三原市の北部に位置する地域で、久井岩海(くいいわうみ)という自然景観が観光スポットとして有名です。読み間違えやすい地名の一つです。
甲山(世羅郡世羅町)
「甲山」、これは「こうやま?」
正解はこうざん!
広島県世羅町にあるこの地名は、昔から山岳信仰の対象とされてきました。甲という字が使われているため、初見ではなかなか読めません。
志和堀(東広島市)
「志和堀」、これは「しわぼり?」と読んでしまいそうですが…
正解はしわほり!
東広島市の北部に位置するこの地名は、かつての志和町に属していた歴史ある地域です。川や山に囲まれた自然豊かな場所で、地元では「しわほり」と普通に使われていますが、県外の方にはまず読めない難読地名の一つです。
河内(東広島市)
「河内」、これって「かわち」じゃないの?
いえいえ、ここではこうちと読みます!
大阪などでは「かわち」と読むことが多いため、広島県の読み方には戸惑う方も少なくありません。東広島市にあるこの地域は、山間部の自然に囲まれたのどかなエリアで、古くからの文化や風習が残る土地です。
まとめ:広島の難読地名、いくつ読めた?
広島県には、初見ではなかなか読めない地名がたくさんありましたね!
地元の人でも間違えやすいものや、歴史的な背景があるものまで、バラエティ豊か。
広島観光の際には、ぜひこれらの地名をチェックして、地元の人との会話のネタにしてみてくださいね!
あなたはいくつ読めましたか?
ぜひ、友達や家族にもクイズを出してみてください!
関連記事