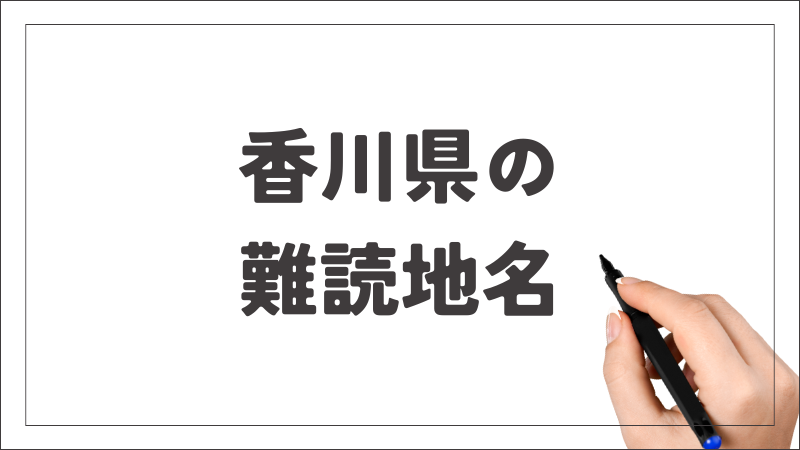いきなりですが、地名クイズです!
「小村」って書いて、なんて読むでしょうか?
「こむら」?「しょうそん」?…
実はぜんっぜん違います!
香川県には、こうした見た目と読みが全然合ってない地名がゴロゴロあります。観光で訪れたときや、地元の人と話すとき、「え?それどう読むの!?」とツッコまれること間違いなし。
今回は、そんな香川県内の読めそうで読めない難読地名を20個ピックアップ!
あなたはいくつ読めるでしょうか?
さっそく見ていきましょう!
関連記事
目次
小村(高松市)
「小さい村」って書いてるから、そのまま読めそうな気がしますよね。
正解はおもれと読みます。
小村は高松市の南部、山間にある地域です。古くから農村地帯として栄えたこの地名は、讃岐弁の古語が語源とも言われています。地元民にとっては馴染み深い読み方でも、県外の人が当てるのは至難の業かもしれません。
鹿角(高松市)
「しかのつの」って、そのまま読んでしまいそうですが…
実はかのつのと読みます。
鹿角は高松市西部の山あいにある地名で、かつて鹿が多く生息していたことが由来と言われています。「しかつの」と読ませないあたりに、地元独自の読みのクセが垣間見えますね。
塩江(高松市)
これはなんとなく「しおえ」って読んじゃいます。
でも本当の読み方はしおのえです。
塩江は高松市の南部にある温泉地としても有名な地域。美しい渓谷と温泉街が広がり、観光客にも人気です。「の」が入るかどうかで印象も大違いですが、現地ではこの読みがスタンダードなんです。
十川(高松市)
漢字だけ見たら「じゅうがわ」か「とおかわ」…?
正しくはそがわと読みます!
十川は高松市の住宅地の一角で、古くは讃岐国の灌漑用水路に由来するとされています。日常的に使われている地名でも、読みが特殊だと案内標識で二度見してしまうかも。
亀水(高松市)
一見、「かめみず」や「きすい」とも読めそうですが…
読み方はたるみです!
高松市の西部に位置する亀水町は、昔から港や漁業と縁の深い地域。「水が溜まる=たるむ」から来ている説もあるようです。読みと漢字のギャップがエグいですね。
磨屋(高松市)
職人の町っぽく「みがきや」と読んでしまいそう。
でも実際はとぎやです。
磨屋町は高松市中心部にある地名で、江戸時代には刃物を研ぐ職人が多く住んでいたことが由来と言われています。「磨屋町商店街」も現存し、今も街の歴史を感じられます。
中間(高松市)
これ、間違いなく「なかま」って読みますよね?
でも香川県ではなかつまと読むんです。
中間町は高松市の中部に位置する地域。町名の由来は“中州”から来ているとされており、昔の地形に由来しています。「なかま」じゃないなんて、ちょっと意表を突かれますね。
仏生山(高松市)
仏、生まれる、山。なんだかありがたそうな名前。
読み方はぶっしょうざんです。
仏生山町は、高松市にある歴史ある寺町エリア。仏生山温泉もあり、観光地としても人気です。ちなみに地元では「ぶっしょうさん」と親しみを込めて呼ばれることも。
赤牛崎(高松市)
「赤い牛と岬」ってことで「あかうしざき」?
実はあかばざきと読みます。
赤牛崎町は、高松市の海沿いにある地名。漁港もあり、古くから水産業が盛んな地域です。「牛」を「ば」と読むのが渋すぎます。まさに難読地名の代表格。
浦生(高松市)
「うらいき」?「うらせい」?…どれも不正解。
読み方はうろです。
浦生町は、かつて海に面していたことから「浦」の字が使われていますが、読みはまさかの「うろ」。一発で読める人は地元民くらいかも。
台目(高松市)
これは「だいめ」と読みたくなります。
でも正しくはうてめと読みます。
台目町は高松市にある農村地域。かつて「台(高台)」の「目(エリア)」として土地を区切っていたことが語源とも言われています。「うてめ」という響き、方言っぽくて味がありますね。
地頭名(高松市)
「じとうめい」?いやいや違います。
読みはじとうみょうです。
地頭名町は高松市南部に位置し、古代の荘園制度に関係あるとされる地名です。「地頭」が直接支配していた土地を「名」と呼んでいたことに由来する、歴史あるネーミングです。
福家(観音寺市)
「ふくや」「ふくいえ」…うーん、惜しい!
正しくはふけと読みます。
観音寺市にある福家町は、讃岐地方でも古くからある地名のひとつ。「家」を「け」と読むパターン、なかなかクセが強いですが、意外と他県にも同様の地名があります。
百相(三木町)
これは絶対「ひゃくあい」って読んじゃいます!
でも正解はもまいと読みます。
百相は三木町の北部にある地域で、由来は定かではないものの、昔の土地の区画や役職名に関係しているとも言われています。どこをどう読んで「もまい」なのか…想像すらつきません。
焼堂(高松市)
「やきどう」?「しょうどう」?
…いや、やけどと読みます!
焼堂町は高松市の山あいにある地域で、火災に関係する伝説が地名の由来とも言われています。文字通りだとちょっと怖い名前ですが、今はのどかな田園風景が広がっています。
除ヶ大向(三木町)
字面だけで心が折れそうなやつ、来ました。
読み方はよけおおむかいです。
三木町の除ヶ大向は、古くからの山林地帯。漢字が多すぎて一瞬フリーズしますが、実は読みやすい響きです。「ヶ」は「が」や「け」ではなく、ここでは「よけ」と読むのがポイント。
弓弦羽(観音寺市)
某フィギュアスケート選手の名前で知ってる人もいるかも?
こちらはゆずりはと読みます。
弓弦羽は観音寺市にある地名で、神話に登場する木「ユズリハ」に由来すると言われています。読みは美しい響きですが、漢字だけ見て当てられる人は少ないはず。
柞(東かがわ市)
一文字シリーズ、来ました。
読みはほうそうです。
柞(ほうそう)は東かがわ市の山間部にある地名。漢字は「くぬぎ(柞)」を意味しますが、なぜ「ほうそう」と読むかは諸説あり。シンプルにして最難関かもしれません。
沺(三豊市)
またもや一文字シリーズ!
正解はさこと読みます。
沺(さこ)は三豊市の地名で、「水がたまる谷地」などを表す古語が語源とされています。これを読めるようになったら、もはや香川県民レベル。
苗羽(小豆島町)
「なえば」?「びょうう」?どちらも不正解。
読み方はのうまです。
苗羽は小豆島町の中心地で、古くは港町として栄えた場所。「苗を羽ばたかせる」と書いて「のうま」、とてもユニークな読み方です。
まとめ:香川県の難読地名、いくつ読めましたか?
いかがでしたか?
香川県には「一見シンプルに見えるのに全然読めない地名」が山ほどあります!
今回紹介した20個、どれも実際に存在する“現役の住所”ばかり。
読み方を知っておくと、旅行や引っ越しのときにも会話のネタになるかも?地名の由来や歴史を知ると、さらに土地への愛着も深まります。
ぜひ、香川県を訪れる際はこの“難読マスター力”を活かしてみてくださいね!
関連記事