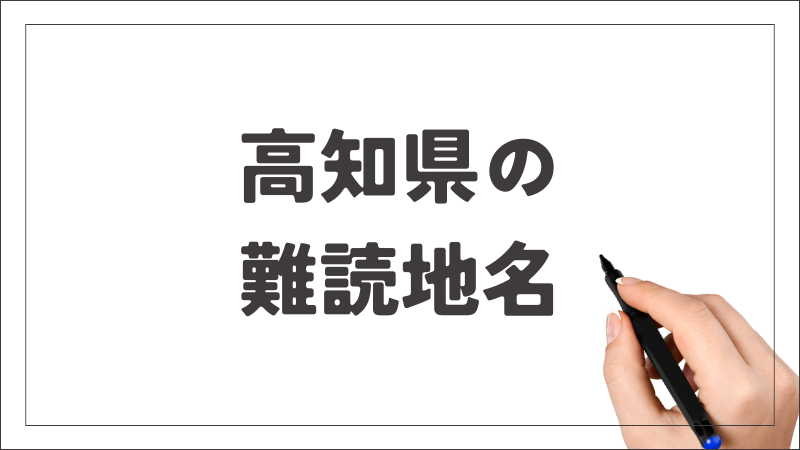高知県って、自然が豊かでのんびりしたイメージありますよね?
でも実は…地名の読み方、めちゃくちゃクセ強なんです!
たとえば「一宮」…「いっきゅう」じゃありませんよ!
地元民なら当たり前でも、他県民は「え?うそやろ…」と読み間違えること必至。
今回はそんな高知県の“読めそうで読めない地名”を20個厳選しました。
歴史や由来もちょこっと紹介しているので、クイズ感覚でぜひ挑戦してみてください。
あなたはいくつ読めますか?
それでは、さっそくいってみましょう!
関連記事
目次
一宮(高知市)
「いっきゅう」や「いちのみや」と読みそうですが…
実は「いっく」と読みます。
高知市にあるこの地名は、古くは土佐国一宮「土佐神社」が鎮座する由緒ある場所。読みは訛って「いっく」となり、地元ではすっかり定着しています。初見では「そんな読みあるの!?」とびっくりされることが多いです。
吸江(高知市)
これ、「すいこう」や「きゅうこう」って読んだ人いませんか?
正しくは「ぎゅうこう」と読みます。
吸江は高知市の浦戸湾近くにある地名で、歴史ある漁港地域のひとつ。漢字の読み方が想像しづらいため、県外からの観光客はまず読めません。地元でも読み間違いネタとして有名です。
魚梁瀬(安芸郡馬路村)
漢字のインパクトがすごすぎるこの地名…。
読み方は「やなせ」です。
「魚梁(やな)」は古代の漁法を指し、「瀬」は浅瀬のこと。馬路村の山あいに位置し、かつて林業で栄えた地域です。地名の由来がそのまま自然と暮らしを表していて、実は意味深い名前なんですよ。
奈半利(安芸郡奈半利町)
「ななり」や「なはりょう」ではありません。
正解は「なはり」です。
奈半利町は高知東部の海沿いにあり、土佐くろしお鉄道の終着駅「奈半利駅」があります。平安時代からの古地名で、由来は「魚が多く生息する川」から来ているとされています。
宿毛(宿毛市)
この漢字、「やどけ」や「しゅくもう」と読みたくなりません?
でも正しくは「すくも」と読みます。
宿毛市は愛媛との県境にある市で、豊かな自然に囲まれています。古語の「すくも(糠の意)」から派生したという説もあり、農業と関わりが深い名前です。
別役(安芸市)
これ、完全に「べつやく」って読みたくなりますね。
ですが「べっちゃく」と読みます。
別役は安芸市内にある地区で、山と川に挟まれた自然豊かなエリア。読みの変化には方言の影響もあり、地元の人にとってはごく普通の発音でも、外から来た人にはかなり難解です。
藻津(宿毛市)
「そうづ」?「もづ」?いやいや…
正解は「むくづ」です。
宿毛市の山間部にある静かな集落で、かつての炭焼き文化や林業の名残が色濃く残っています。「藻」や「津」が付く地名は全国にありますが、「むくづ」という読みはかなり珍しい部類です。
鍵掛(土佐清水市)
「かぎかけ」って素直に読みたいところですが…
実は「かいかけ」です。
土佐清水市の山間部にある地域で、険しい地形と複雑な山道が特徴。その昔、山の入り口に“鍵”のような岩場があったことが名前の由来という説もあります。
爪白(土佐清水市)
「つめしろ」や「そうはく」と読む人、意外と多いです。
読み方は「つまじろ」です。
足摺岬の近くにある漁村で、海の景色が美しい場所。昔はクジラ漁も行われていたとか。名前の由来は定かではないですが、「端(つま)」+「白浜(しら)」からきている説もあります。
神母ノ木(香美市)
読み方に自信ありますか?「しんぼのき」じゃありません。
正解は「いげのき」です。
香美市の山間にある小さな集落で、自然と神話が融合したような神秘的な名前。「神母」は「いげ」と読ませる特殊な当て字で、地元でも読みを知らない若者が増えてきています。
手結(香南市)
「てむすび」じゃないし、「てけつ」でもありません!
これは「てい」と読みます。
香南市の港町で、観光スポット「手結港可動橋」でも知られています。名前の由来は「手結い=共同作業の象徴」からきているとも。短い読みながら、誤読率の高い地名です。
兎田(高岡郡四万十町)
「うさぎた」「とでん」…どちらも不正解。
正しくは「うさいだ」です。
高岡郡四万十町の山間部にある集落で、名前から可愛らしさを感じますが、実際はかなり険しい山道の先にあります。兎のような形の山が近くにあることが名前の由来とも言われています。
甲浦(安芸郡東洋町)
「こううら」じゃありません!
正解は「かんのうら」です。
徳島県との県境に近い海沿いの町で、海の幸が豊富な港町です。昔は「神の浦」とも呼ばれていたという説があり、霊験あらたかな由来を持つかもしれません。
淌濤(安芸郡田野町)
これが読めたらすごい!
読みは「しょうとう」です。
安芸郡田野町にある非常に珍しい地名。漢字の画数も多く、読むのも書くのも難しいですが、地域の伝統行事や神事が盛んな場所で、地元民にとっては誇りある地名です。
二タ又(安芸郡北川村)
「にたまた」じゃないの?
でも実は「ふたまた」なんです。
北川村の山間にあり、文字通り川が分かれる「二股」にちなんで名付けられたと言われています。シンプルに見えて、読みを外しやすい地名の代表例です。
和食(安芸郡芸西村)
「わしょく」ではありません!笑
正しくは「わじき」です。
芸西村にある海沿いの地域で、漁業が盛んなエリア。「和食(わじき)」駅も存在します。名前だけ見ると日本料理の話かと誤解されがちですが、立派な地名です。
後免(南国市)
「あとめん」?「うしろゆるし」?どちらもブブー。
これは「ごめん」と読みます。
南国市にある町名で、JR「後免駅」もあります。名前の由来は「ご免状」による市の開設から来ていると言われており、歴史的背景のある由緒正しい地名です。
半家(四万十市)
「はんけ」「なかばや」ではなく…
正解は「はげ」です。
四万十川流域にある集落で、かつての地元藩士の姓に由来するという説もあります。鉄道ファンには予土線の難読駅名としてもおなじみです。
高石(高岡郡中土佐町)
「たかいし」じゃないですよ?
読み方は「たこす」です。
中土佐町の漁港近くにある集落で、漢字とのギャップが激しすぎる地名のひとつ。「タコ」とは無関係ですが、名前のインパクトは抜群です。
鵜来巣(高知市)
「うらす」や「うくすい」ではありません。
正解は「うくす」です。
高知市の鏡川上流にある集落で、読みが難しいだけでなく、文字もめずらしい。野鳥の「鵜(う)」が群れる場所だったことが地名の由来とされます。
まとめ:高知県の地名、侮るなかれ!
いかがでしたか?
高知県には、地元民でも一瞬戸惑うような難読地名がたくさんあります!
自然豊かでのんびりした県のイメージとは裏腹に、地名は一筋縄では読めない個性派ぞろい。
旅行の際や地図を見ている時に、「これ読めるよ!」って言えたらちょっとカッコいいかも?
地名って、読み方ひとつで歴史や文化が見えてくるからおもしろいですよね。
ぜひ次回の高知旅では、この知識を活かしてみてください!
関連記事