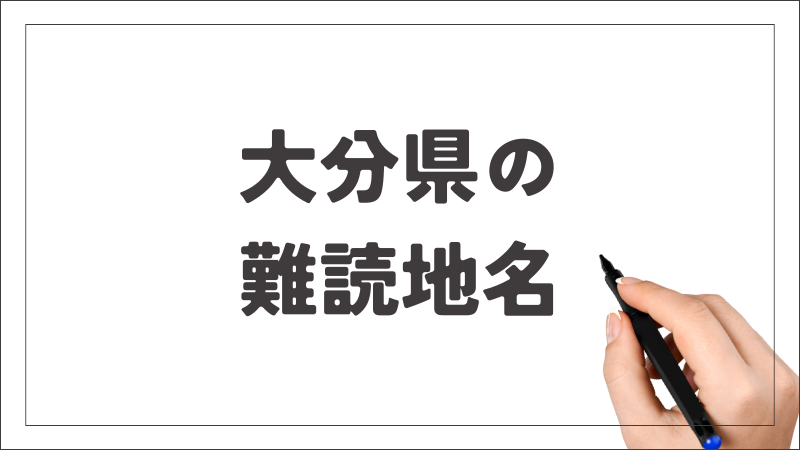「大分県の地名って、意外と読めないの多くない?」
…と思ったあなた、正解です。
たとえば「豊饒」って書いて、読めますか?
「ほうじょう」ではありませんよ〜!
今回は、大分市を中心に、大分県内で「読めそうで読めない」クセ強な難読地名を20個ピックアップしました。
どれも現役の正式住所表示で、地元の人以外には読めないものばかり。
読み方だけじゃなく、その地名の由来やちょっとした小話も添えてお届けします。
読み仮名当てクイズ感覚で、楽しんでいってくださいね!
関連記事
目次
丹川(大分市)
この字面、どう見ても「たんがわ」って読みたくなりますよね。
でも実際は「あかがわ」と読みます。
丹川は大分市東部に位置する地域で、「丹」は「赤土」や「朱色」を意味する漢字。昔は赤い土壌が広がっていたことが地名の由来とも言われています。自然豊かな山あいにあり、釣りやハイキングスポットも多いエリアです。
明磧(大分市)
「めいせき」や「みょうがわら」って読みたくなる人、いません?
実はこれ「あけがわら」と読むんです。
明磧は、大分市の中心部から少し外れた住宅街。昔は川沿いの「河原」だった場所で、「磧(かわら)」は古語で「河原」を意味します。漢字のインパクトが強すぎて、初見だと正解までたどり着けない人が多い地名です。
生石(大分市)
「なまいし」とか「せいせき」って読んじゃいそうですね。
でもこれ、正しくは「いくし」です。
生石は大分市西部の山間部に位置するエリア。由布岳のふもとにあたり、「生きている石=霊石」が祀られていたという伝承があるとか。神秘的な由来とセットで覚えると、ちょっとロマンを感じる地名です。
荏隈(大分市)
これ、「えぬま」って読んだ人、挙手!
正解は「えのくま」です。
荏隈は大分市南部の住宅街。古くは「荏胡麻(えごま)」が自生していた地で、「隈」は「すみっこ」や「入り組んだ場所」を意味します。植物の名前に由来する地名って、意外と読みづらいのが多いんですよね。
大志生木(大分市)
字の数が多くて、読む前からちょっと諦めそう…。
でも頑張って読んでみてください。「おおじゅうき」です!
大志生木は大分市西部に位置し、のどかな田園風景が広がる地域。「生木(じゅうき)」はかつて木工職人の集落があったことに由来するとか。大分の地名マニアにとっては、外せない難読スポットです。
鴛野(大分市)
これ、「うしの」って読みたくなりませんか?
でも正しくは「おしの」です。
鴛野は大分市東側にあるベッドタウン的な地域。「鴛」は「オシドリ」の意味で、昔はこの鳥がたくさん生息していたと伝えられています。動物由来の地名も、漢字で書かれると一気に読めなくなる典型例ですね。
賀来(大分市)
「がらい」?「かくる」?なんとなく読めそうで読めない…。
答えは「かく」です。
賀来は大分市内でも歴史ある地域のひとつで、古くからの集落が残るエリア。賀来神社などの名所もあり、地元では馴染み深い名前。漢字自体はシンプルなのに、読みが完全に想像外なのが面白いですね。
椎迫(大分市)
「しいはく」って言いたくなりますよね。
でも読み方は「しいざこ」です。
椎迫は自然豊かな山あいのエリアで、漢字の「迫」は「谷」や「せまい土地」を指すことがあります。「椎」は木の名前。山と木の地形が由来の、いかにも昔の日本らしい風景の地名です。
志生木(大分市)
「ししょうぎ」や「しゅうぼく」…なかなか迷いますよね。
正解は「しゅうき」です。
志生木は大分市の郊外にある地域。農村地帯が広がっていて、現在ものどかな雰囲気が残っています。「志」と「木」が入っているので立派な名前に見えますが、読み方はスッキリ一言「しゅうき」です。
寒田(大分市)
「さむた」じゃないの?って思ったあなた、惜しい!
実は「そうだ」と読みます。
寒田は大分市の郊外にあるエリアで、「寒川」「寒原」などと同じく、寒さに関係する漢字が使われていますが、読みは少しひねりあり。地元のバス停にも使われている名前で、読み方を知ってるとちょっと通っぽいかも。
高尾水分(大分市)
読めそうで読めない難読コンボネーム、来ました!
これで「たかおみくまり」と読みます。
高尾水分は大分市の南西に位置する地域。「水分(みくまり)」は「水を配る神」を意味し、水源地や水神信仰のある土地に見られる名前。読みのリズムが独特すぎて、一発で読めたら天才級です。
東院(大分市)
これ、「ひがしいん」じゃないの?って言いたくなる気持ち、わかります。
でも正解は「とい」です。
東院は大分市中心部に位置し、古くからの町名が残る地域。「院」はお寺や施設の意味もあり、平安時代からの歴史が由来とされています。コンパクトな漢字なのに全然読めない系の代表格ですね。
豊海(大分市)
「ほうかい」「ゆたかうみ」などと読んだ方、ちょっと違います。
これは「とよみ」と読みます。
豊海は大分市東部の海に近いエリア。「豊かな海」から名付けられたとも考えられますが、昔は漁業が盛んだった地域でもあり、今でも海の香りが漂う場所。読み方の響きも優雅でいいですよね。
那知椰(大分市)
これ、もはや読める気がしない…という人も多いかも。
正解は「なちなぎ」です。
那知椰は大分市の山あいに位置する、かなりマニアックな地名。2文字目の「椰(やし)」が特にクセモノで、読み方の予測が困難です。地元の人でも間違えることがあるそうで、まさに難読地名界の伏兵。
端登(大分市)
「たんとう」?「はしのぼり」?どれも惜しい…。
でも読み方は「はたのぼり」です。
端登は大分市の郊外にある、山と田んぼに囲まれた地域。かつては村落が点在していたことから、登っていく道の端という意味でこの名がついたとも。漢字の雰囲気は硬派ですが、読み方は柔らかめ。
豊饒(大分市)
「ほうじょう」じゃないんです。残念!
これは「ぶにょう」と読みます。
豊饒は大分市の中でも特に読みにくいと有名な地名。「饒」の字がクセ強で、当て字っぽく見えてしまいます。実際の地名として使われていることに驚く人も多く、知る人ぞ知る“難読の王様”かもしれません。
古国府(大分市)
「こくふ」って読みそうになりますが、違います!
正解は「ふるごう」です。
古国府は、大分市中心部にある地域で、昔の「国府(こくふ)」の跡地とも言われています。「国府」は律令制時代の地方行政機関のことで、「古い国府=ふるごう」という名称になったとされます。
戸次(大分市)
「とつぎ」「とじ」…なかなか正解にたどり着けない地名ですね。
正解は「へつぎ」です。
戸次は大分市南部にある歴史ある町で、戦国武将・戸次鑑連(へつぎ あきつら)ゆかりの地としても知られています。読み方に慣れれば、「あ、あの武将の…」と思い出す人もいるかも。
戸保ノ木(大分市)
「とほのき」「とぼのき」などと読まれがちですが…
これは「へぼのき」と読みます。
戸保ノ木は、大分市南部にある小さな集落。地名の由来は諸説ありますが、林業や自然に関係する地名であることは確か。珍しい読み方と素朴な響きが魅力的な、隠れた難読名所です。
政所(大分市)
「まさしょ」や「せいしょ」と読んだ方、残念!
正しくは「まどころ」です。
政所は大分市の郊外に位置し、昔の役所的な機能を持っていた場所に由来します。「所」は読めても「政」の読みが意外で、ちょっとしたトラップ地名。古地名の名残を感じさせる、歴史あるエリアです。
まとめ:大分県の難読地名、いくつ読めた?
いかがでしたか?
大分県には、思わず「え、これでそう読むの!?」と声が出そうな地名がたくさんあります。
地元の人には当たり前でも、外から来た人にとっては完全に初見殺しの嵐…。
でもこういう“読めないけどおもしろい地名”って、知れば知るほどクセになりますよね。
今回紹介した20個の地名、ひとつでも読めたらすごいかも?
旅先やドライブ中に見つけたとき、ちょっとドヤ顔で読み方を披露できるかもしれません♪
あなたの地元にも、まだまだ知られざる難読地名が眠っているかも…!
気になった方は、ぜひ探してみてくださいね!
関連記事