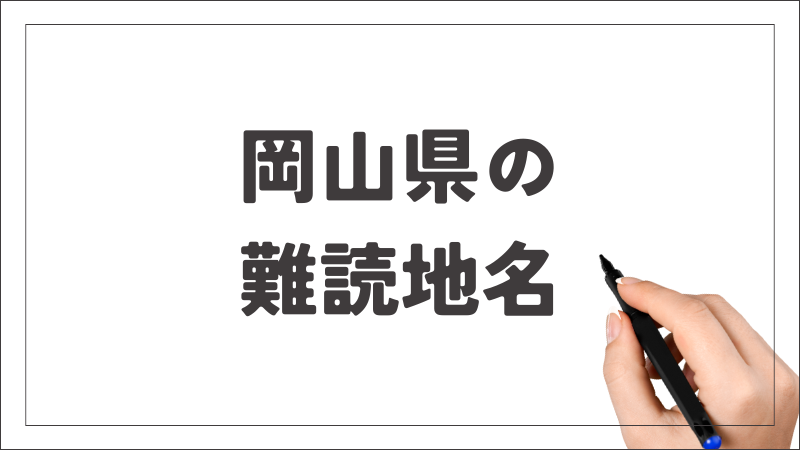突然ですが、クイズです!
「穝」これ、どう読みますか?
正解は… さい と読みます!
「え?そんな読み方するの?」と驚いた人も多いのではないでしょうか?
岡山県には、こんな感じで初見では読めない難読地名がたくさんあります!
普段見慣れている漢字でも、地名になると全然違う読み方をすることが多いんですよね。
この記事では、岡山県の超難読地名を20個ご紹介します!
由来や歴史も交えながら紹介するので、「なぜそんな読み方なのか?」も合わせて楽しんでくださいね。
あなたはいくつ読めるでしょうか?
さっそく見ていきましょう!
関連記事
目次
穝(岡山市中区)
「この漢字、そもそも見たことない…!」なんて人もいるのでは?
実は さい と読みます。
「穝」という漢字は、「新しい」や「穀物が実る」などの意味を持つ古い字。岡山市のこのエリアでは昔から使われている地名ですが、全国的にはあまり見かけません。読み方を知らないと「これ何て読むの?」と戸惑ってしまうこと間違いなしです!
妹尾(岡山市南区)
「妹」に「尾」だから…「いもうとお?」「せつび?」
実は せのお と読みます。
この地名は、古くから続く地名で、妹尾という姓にも使われています。岡山市南区のこの地域は、歴史的に交通の要所として栄えてきたエリア。今でも地元の人々には馴染みのある地名ですが、初見では読めない人がほとんどです!
撫川(岡山市北区)
「撫でる」に「川」だから…「なでがわ?」
正解は なつかわ です。
「撫」という漢字には「やさしくさする」という意味がありますが、ここでは「なつ」と読むのがポイント。岡山市北区のこのエリアは、江戸時代から続く宿場町として知られています。古くからの歴史が残る土地だからこそ、独特な読み方が受け継がれているんですね。
蕃山町(岡山市北区)
「蕃」って普段あまり見かけない漢字ですよね。
正解は ばんざんちょう です。
「蕃」という字は「繁栄する」「広がる」という意味を持っています。かつてこの地には蕃山という山があり、その名を取って町名になりました。岡山市の中心部に位置するこの町は、現在も歴史的な雰囲気を感じさせる場所として知られています。
日吉町(倉敷市)
「日吉」といえば「ひよし」?でも、岡山では…
実は ひよせちょう と読みます。
「日吉」という地名は全国各地にありますが、岡山県倉敷市では「ひよせ」と読むのが特徴。歴史的にこの地は信仰の対象とされた場所であり、神社や古い町並みが残っています。観光地としても知られていますが、地名の読み方を知らないと迷ってしまうかも?
妹(倉敷市)
これはどう読むの?「いもうと?」「まい?」?
実は せ と読みます。
「妹(せ)」という読み方はとても珍しく、岡山県の地名特有のものです。倉敷市真備町は、歴史的に備中国の一部であり、奈良時代の学者・吉備真備ゆかりの地としても知られています。地元の人には馴染み深い地名ですが、県外の人が初見で読めることはほぼないでしょう。
祐安(倉敷市)
「祐」と「安」で「ゆうやす?」
正解は すけやす です。
「祐(すけ)」という読み方は、名前などでは使われることがありますが、地名で見ることは珍しいですね。倉敷市のこの地域は、歴史的な背景を持ち、古くから農業が盛んな場所でした。現在も穏やかな住宅地として、多くの人が暮らしています。
美袋(総社市)
「美しい袋」ってことで「びたい?」「みのう?」
実は みなぎ と読みます。
美袋という地名は、かつてこの地に水が豊富で「水長(みなが)」と呼ばれていたことが由来と言われています。総社市のこの地域は、JR伯備線の美袋駅があることでも知られています。読み方を知らないと、地元の駅のアナウンスで「え、今なんて言った?」と戸惑うこと間違いなし!
宍粟(総社市)
「宍道湖(しんじこ)」の「宍」に似てるけど…「しそう?」
実は しさわ と読みます。
「宍粟(しさわ)」は、全国的には兵庫県宍粟市(しそうし)が有名ですが、岡山県総社市にも同じ漢字を使う地名があります。もともとは「肉が豊かにある」という意味を持ち、古くから農村地帯として栄えてきました。歴史ある地名なので、地元の人には馴染み深いですが、初見では絶対に読めませんよね!
刑部(総社市)
「刑部」ってまるで法務省の役職みたいだけど…「けいぶ?」
実は おしかべ と読みます。
「刑」は、古代の言葉が由来とされています。総社市の刑部地区は、昔から開けた農村地帯であり、地元では「おしかべ」という名前で親しまれています。この読み方、知らなかったら絶対に「けいぶ」って読んじゃいますよね!
矢掛町(小田郡)
「矢を掛ける」から「やかけ?」それとも「やがい?」
正解は やかげちょう です。
矢掛町は、江戸時代に宿場町として栄えた歴史のある場所。西国街道の宿場町として、今も歴史的な建造物が残っています。「矢掛」の由来には諸説ありますが、矢を射る際に「掛ける」ことが関係しているとも言われています。宿場町巡りをするときに、ぜひこの地名の由来も思い出してくださいね!
邑久(瀬戸内市)
「邑」って読みにくいけど…「むらく?」「おうきゅう?」
実は おく と読みます。
「邑(おく)」は、昔の言葉で「村」「集落」を意味します。瀬戸内市邑久地区は、歴史的に瀬戸内海の海運と関係が深い地域で、古くから人が住んでいたことが分かっています。現在も美しい景観とともに、伝統的な文化が残るエリアです。
呰部(真庭市)
「呰」ってそもそも見たことないんだけど…「しぶ?」「あざ?」
正解は あざえ です。
この珍しい「呰(あざ)」という漢字は、古くから岡山の地名に使われており、今も一部の地名として残っています。真庭市の呰部は、山間の自然豊かな地域で、伝統的な暮らしが残る場所です。初めて見ると絶対に読めない難読地名の代表格ですね!
鯰(美作市)
「鯰(なまず)」って、普通に読めそうだけど、地名だと何か違う?
そのまま なまず と読みます!
美作市にあるこの地名は、魚の「ナマズ」と同じ漢字ですが、地名として使われているのが珍しいポイント。昔からこの地域の川や池にナマズが生息していたことが由来とも言われています。シンプルな読み方だけど、「本当にそのまま読むの?」と疑ってしまう難読地名の一つですね。
尺所(和気郡和気町)
「尺所」って「しゃくしょ?」「せきしょ?」それとも…?
正解は しゃくそ です!
「尺(しゃく)」は長さの単位として有名ですが、「所(そ)」と組み合わさることで、独特な地名の読み方になっています。和気町のこの地域は、歴史的に宿場町や交易の場として利用されていたとされ、昔の測量や区画と関係があるとも言われています。まさに、地名の由来を知ると「なるほど!」となる難読地名ですね!
浅海(小田郡矢掛町)
「浅海」だから「あさうみ?」それとも「せんかい?」
正解は あすみ です!
「浅海(あすみ)」という地名は全国的にも珍しく、岡山県の矢掛町にだけ存在する独特な読み方です。かつてこの地には浅い川や湿地帯が広がっていたことが由来とされています。今では水田地帯が広がる穏やかな地域ですが、この読み方を知っている人はかなりの地元通ですね!
至孝農(苫田郡鏡野町)
「至孝農」って、めちゃくちゃ漢字が難しい!「しこうのう?」
実は しこうの と読みます。
「至孝」は「非常に孝行なこと」を意味し、「農」と合わさることで、古くから農業が盛んな地域であったことを示しています。鏡野町は岡山県内でも特に自然豊かなエリアで、この地名にも長い歴史が刻まれています。初見では絶対に読めない、超難読地名の一つですね!
石生(勝田郡勝央町)
「石生」って「せきしょう?」それとも「いしなま?」
正解は いしゅう です!
「石(いし)」はそのままですが、「生(う)」と読むのがポイント。この地名の由来は、昔この地に大きな岩があったことに関係していると言われています。岡山県内でもあまり知られていない地名ですが、地元の人には馴染み深い地域の一つです。
安ヶ乢(久米郡久米南町)
「安ヶ乢」って、、そもそも「乢」って何?
そう、正解は やすがたわ です!
「乢(たわ)」という字は、山の谷間や峠を意味する言葉で、西日本の地名に時々見られます。久米南町にあるこの地域は、まさに山間部に位置し、昔から峠道として利用されていました。独特な字を使った、まさに「難読地名」と言える一つですね!
東垪和(久米郡美咲町)
「垪和」って、そもそもどう読むの!?「ひがしへいわ?」
正解は ひがしはが です!
「垪和(はが)」という地名は、美咲町に複数存在しており、「西垪和」「東垪和」などと地域ごとに分かれています。古くから農村地域として発展してきた歴史を持ち、美しい田園風景が広がるエリアです。「垪(は)」という漢字が珍しいため、初見では全く読めない地名ですね!
まとめ:岡山県の難読地名
いかがでしたか?
岡山県には、全国的に見ても珍しい読み方をする地名がたくさんありますね!
地元の人には当たり前でも、初めて見ると「こんな読み方するの?」と驚いてしまうものばかり。
次に岡山を訪れる際には、ぜひこの難読地名を話題にしてみてください!
ちょっとしたトリビアとしても使えるので、友達や家族とクイズ感覚で楽しんでみてはいかがでしょうか?
それでは、また次回の難読地名特集でお会いしましょう!
関連記事