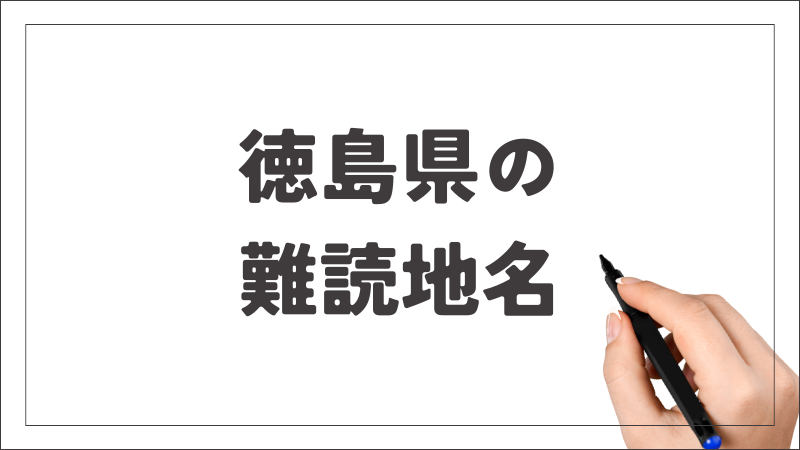徳島県って、実は読めそうで読めない地名の宝庫なんです。
たとえば「麻植」…これ、どう読みますか?
「あさうえ」?いやいや、そんなに素直じゃないんです。
地元の人には当たり前でも、他県の人が見たら「ん?」ってなってしまう地名がゴロゴロ。
今回は、そんな徳島県内の難読地名を20個ピックアップ!
読み方のクセや由来を交えながら、クイズ感覚で楽しめる内容にしました。
さて、あなたはいくつ読めますか?
関連記事
目次
鮎喰(徳島市)
見た瞬間「さかな系かな?」って思いますよね。
実はあくいと読みます。
鮎喰は、徳島市の西部に位置する地域で、鮎喰川の流域に広がっています。地名の由来もこの川にちなんだものとされていますが、「あゆくい」ではなく「あくい」と読むところに、クセの強さを感じます。地元の人以外にはなかなか馴染みがない地名かもしれません。
助任(徳島市)
「じょにん」?「すけにん」?って迷うやつ。
正解はすけとうです。
助任は徳島市の中心部に位置し、交通の便も良い住宅街です。由来には諸説ありますが、地名が人名のようにも見えるため、初見で読める人は少ないでしょう。徳島駅周辺に住んでいる人ならピンとくるかもしれませんが、県外の人には難解です。
勝占(徳島市)
なんだか縁起が良さそうな地名ですが…
実はかつらと読みます。
勝占は、徳島市の南部に位置する地域で、住宅地としても発展しています。「勝つ」と書くので「しょうせん」や「かつせん」と読まれがちですが、まさかの「かつら」。このギャップに驚く人が多い地名です。
府中(徳島市・国府町)
「ふちゅう」じゃないの!?って思った人、仲間です。
正解はこうです。
府中は、徳島市国府町にある歴史ある地名で、古代には「阿波国府」が置かれていた場所です。「府中」は全国に多数ありますが、「こう」と読むのは珍しく、古代の行政区画に由来する読み方なんだとか。国府町の“国府”ともリンクしていますね。
西沢(徳島市・国府町)
「にしざわ」じゃないの?という声が聞こえてきそうです。
読み方はにっそです。
徳島市の国府町にあるこの地名は、地元でも「にっそ」の響きで親しまれています。意外な読み方に驚く人も多く、初見で正解するのは至難の業。「西」が「にっ」と読むのもクセ強ポイントです。
矢三(徳島市)
これ、「やさん」って読んじゃいそうですよね。
実はやそと読みます。
矢三は徳島市の北部にあるエリアで、大学や住宅街が広がっています。「三」で「そ」と読ませるあたり、なかなかのトリッキーさ。通称「矢三交差点」は交通の要所でもありますが、読み方は地元民でないと通じにくいかも。
撫佐(鳴門市)
優しそうな地名だけど、読み方はけっこう難しいです。
これはむさと読みます。
撫佐は、鳴門市の北西部に位置する地名で、自然に囲まれたのどかなエリアです。「撫でる」に「佐」という漢字の組み合わせは、音読みも訓読みも当てにくく、まさに難読地名の代表格といえるでしょう。
撫養(鳴門市)
「なでやし」って読んだ人、惜しいです。
正解はむやです。
撫養は鳴門市の中心市街地を含む地名で、かつては「撫養町」としても存在していました。「むや」は古い日本語の響きを残す読み方で、地名の歴史的背景を感じさせます。鳴門駅周辺の住所でもよく見かけます。
中田(小松島市)
どう見ても「なかた」じゃないんです。
実はちゅうでんと読みます。
小松島市の中心部にあるこの地名は、住宅地として発展しているエリアです。中学校名などにも使われているので地元では馴染み深い読み方ですが、初見だと完全に“引っかけ問題”に見えてしまいますね。
神宅(上板町)
「かみたく」や「じんたく」じゃありません。
これはかんやけと読みます。
神宅は、徳島県の上板町にある地名で、古くから農村として栄えてきた地域です。「やけ」は屋敷(やけ)に通じる読みで、神にまつわる伝承があるとも言われています。文字の印象からは予想しづらい読み方です。
麻植(吉野川市)
これは一見「まうえ」や「あさえ」って読んでしまいがち。
正解はおえです。
麻植は、吉野川市の旧・鴨島町エリアを中心に存在する地名で、かつては「麻植郡」としても使われていました。歴史的な郡名が今も地名として残っている珍しいケースで、「麻」と「植」という字面からは読みが想像しにくく、まさに難読の王道です。
工地(阿南市・那賀川町)
「こうち」じゃないの?って思いますよね。
実はたくむじと読みます。
工地は、阿南市那賀川町にある地名で、農村風景が広がる地域です。漢字だけ見ると「こうち」や「くじ」と読んでしまいそうですが、実際にはかなり珍しい読み方。地元の人以外にはまず読めない、隠れ難読地名です。
落雷(阿南市)
これは完全に気象用語。「らくらい」でしょ?と思いきや…
正解はおちらいです。
落雷は、阿南市の南部にある地名です。字面からして“ド直球”の漢字なのに、まさかの「おちらい」という読み方。雷が落ちるイメージとは裏腹に、静かな田園地帯が広がるのどかな地域です。
学原(阿南市)
つい「がくはら」と読んでしまいたくなりますが…
答えはがくばらです。
阿南市の山間部にある地名で、かつての集落名としても使われていました。「ばら」は、原(はら)の音便変化とされ、四国各地でも見られる方言的な読み方の名残です。親しみやすい音ですが、初見では迷うこと必至。
権現池(阿南市)
「ごんげんいけ」かな?と想像する方、多いはず。
そのままです!ごんげいけと読みます。
阿南市にあるこの地名は、神社の御神体とされる「権現」に由来しています。古くから神聖な水源として知られており、地域住民にとっても信仰の対象となってきました。「池」とつくことから、農業用水や灌漑にも使われていたようです。
十八女(阿南市)
これ、「じゅうはちおんな」って読んだ人、正直に挙手!
正解はさかりです。
阿南市の東部に位置する十八女(さかり)は、かなりクセ強めな地名。古くは“さかり”という音の地名に、当て字として「十八女」が使われたと言われています。なぜこの漢字が?と思わせる一例ですね。
紫衣池(阿南市)
高貴な響きだけど…「しえいけ」じゃないんです。
実はしいけと読みます。
紫衣池は、阿南市の郊外にある地名で、かつての農業用の池が地名の由来とされています。「紫衣」と書いて「しい」と読むのは非常に珍しく、仏教用語や歴史的背景に由来があるとも。ロマンを感じる地名のひとつです。
椎木谷(阿南市)
「しいのきだに」…一瞬スッと読めそうですが。
実際そのまましいのきだにです。
阿南市の山間部にある地名で、椎の木が茂る谷間を意味しています。読み方自体はそこまで難しくありませんが、字面が渋く、インパクトのある地名。自然由来の地名として、地域の風土が色濃く反映されています。
〆谷(阿南市)
なんだこの記号!?って驚いた方も多いのでは?
これはしめだにと読みます。
阿南市にあるこの地名は、記号のような「〆(しめ)」が正式な漢字として使われている点で、全国的にもかなり珍しい存在です。名前の由来には、谷を“締める”ように位置していたことから来たという説もあります。
竹鼻(阿南市)
「たけはな」…普通に読んじゃいそうですが…
正しくはたけのはなです。
阿南市南部にあるこの地名は、竹林が広がっていた丘陵地に由来しています。「の」が入ることで一気に難読に。ちなみに「鼻」は“突き出た地形”を表す意味もあり、地形と読み方がリンクしている興味深い地名です。
まとめ:徳島県の難読地名
いかがでしたか?
徳島県には、意外と知られていない“クセ強”な読み方の地名がたくさんあります。
漢字を見て素直に読もうとするとハズすことも多く、まさに難読地名の宝庫!
旅行や仕事で徳島を訪れる機会があったら、ぜひ現地で「読めたらスゴい!」と話題にしてみてください。
地元の方との会話のきっかけにもなるかもしれませんよ。
また他の都道府県の難読地名も順次紹介していくので、そちらもお楽しみに!
<div class="st-editor-margin" style="margin-bottom: -5px;">
関連記事
<a href="https://nandoku-chimei.com/tokushima-stationname/">⇒徳島県の【難読駅名】はコチラ!</a>