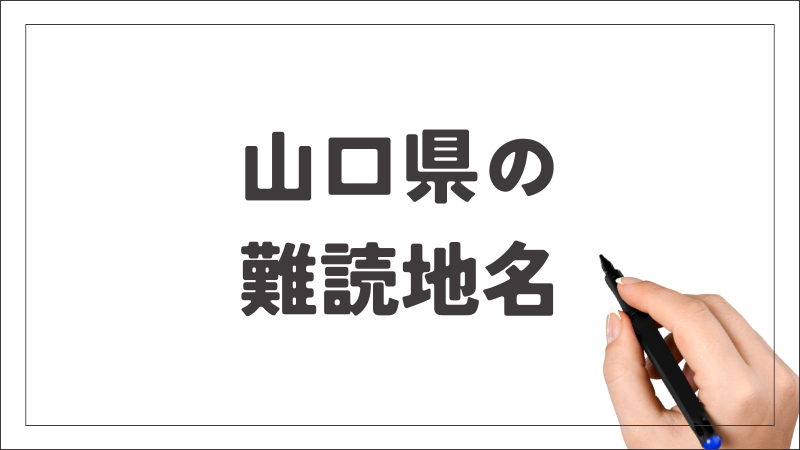いきなりですが、山口県の地名クイズです!
「特牛」…これ、なんて読むか分かりますか?
正解は「こっとい」!
地元民じゃないと一生読めないかもしれません(笑)。
山口県には、こんなふうに見た目と読みが全然違う“クセ強地名”がたくさんあるんです。
今回は、そんな山口の“読めそうで読めない”難読地名を20個厳選!由来や歴史も交えて紹介していきます。
旅行や引っ越し前にチェックしておくと、会話のネタにもなるかも?
あなたはいくつ読めるでしょうか?
それではさっそく見ていきましょう!
関連記事
目次
内日(下関市)
「内日」…つい「ないにち」や「うちにち」って読んじゃいそう。
実は「うつい」と読みます。
下関市の北部、山あいに位置する自然豊かな地域です。内日は「内の谷」から転じたとされ、内陸部の静かな集落として昔からの風景を残しています。地元では読み方が当たり前でも、他地域の人にはまず読めません!
阿内(下関市)
これ、「あない」か「おうち」か迷いません?
正解は「おうち」と読みます。
下関市東部に位置する阿内は、古くは村落単位で存在していた歴史ある地名です。地元では「おうち地区」と呼ばれて親しまれており、今も田園風景が残るのどかな地域です。初見ではかなり難易度高め!
員光(下関市)
これは「いんこう」と読んでしまいそう。
正しくは「かずみつ」と読みます。
旧豊田町にあたる地域で、名字としても見かけることがあります。「員」は“かず”と読む場合があり、「光」はそのまま“みつ”。地名の読み方としては非常にレアですが、現地では普通に使われている名称です。
轡井(下関市菊川町)
「轡」って漢字がまず読めませんよね…。
読み方は「くつわい」です!
菊川町にあるこの地名、「轡」は馬具の「くつわ」を表しており、かつて馬に関連する文化や地形があったとも考えられています。歴史や産業が語源になっているケースは多く、難読地名にはよくあるパターンですね。
樅ノ木(下関市菊川町)
「樅ノ木」って、なんだか木の名前そのまま?
そう、「もみのき」と読みます。
針葉樹の「樅(もみ)」から来ており、古くからその木が多く生えていた地域に付けられた地名と考えられます。自然豊かな菊川町らしさが感じられる地名です。読みやすそうに見えて意外と読めないかも?
特牛(下関市)
「特牛」…「とくぎゅう」じゃないの?
答えは「こっとい」です!
この地名、読みと意味がまったくリンクしてない難読地名の代表格。下関市豊北町にある地域で、「こっとい漁港」などが有名です。昔の方言が語源になっている説もあり、観光客泣かせの地名として有名です。
木屋川(下関市)
「きやがわ」?「もくやがわ」?
正解は「こやがわ」です。
下関市を流れる川の名前でもあり、その周辺地名として使われています。「木屋」という言葉には昔の工房や職人の家という意味もありますが、ここでは純粋に地名として「こやがわ」と読むのが正解です。
杢路子(下関市豊田町)
「杢」ってそもそも読めない…。
でも「むくろうじ」と読みます。
「杢」は職人を意味し、「路子」は道にまつわる意味合い。古くからの職人町、あるいは街道沿いの集落だったことが伺えます。今ではほぼ使われない漢字だけに、難読ぶりはかなりのものです。
八道(下関市豊田町)
「はちどう」かな?いや「やつみち」?
実は「やじ」と読みます!
読み方の由来は諸説ありますが、古代の道路網「八道(はちどう)」とは別物のようです。地元では昔から「やじ」と呼ばれており、外部の人が正解できる確率はかなり低め。
南部町(下関市)
「なんぶちょう」って読んじゃいそう…。
でも正解は「なべちょう」です!
山口県では珍しい「なべ」と読む地名のひとつ。由来ははっきりしませんが、かつての役場や学校名にも使われており、正式な住居表示として残っています。日常会話では普通に使われているようです。
岬之町(下関市)
「岬」までは読めても、後ろがちょっと引っかかりますよね。
これは「はなのちょう」と読みます。
「岬」は“はな”とも読むことがあり、地形的に突き出た場所などを指します。「岬之町」は、下関駅近くの街中にある歴史ある地名で、レトロな雰囲気も残る人気エリアです。読めるようになるとちょっと得意気になれるかも?
蓋井島(下関市)
「蓋井島」…「ふたいじま」って読みたくなりますよね。
でも正解は「ふたおいじま」です!
下関市の沖にある小さな島で、人口はわずか数十人。漁業の島としても知られています。「蓋井」の読み方には諸説ありますが、「ふたおい」は古い地名が由来とされ、今も地元で大切に使われています。
櫟原(宇部市)
「櫟」って漢字からして難しすぎる…
これは「いちいばら」と読みます!
「櫟(いちい)」は木の名前でもあり、「原」はそのまま“はら”。自然豊かな場所を想像させる名前です。宇部市の郊外に位置しており、かつては農村として栄えた歴史ある地域です。読めたらかなりの漢字通!
棯小野(宇部市)
こんな漢字、初見じゃムリすぎる…。
でも「うつぎおの」と読みます。
「棯(うつぎ)」は植物の名前、「小野(おの)」は野原のこと。地名としては古くから存在しており、自然の地形や植生に由来した命名と考えられています。漢字の読み方からしてマニアックなので、読める人は相当すごい!
吉部(宇部市)
これは「よしべ」?いや「きべ」?
正解は「きべ」と読みます!
宇部市北部にある自然豊かな山間の地域です。名字としても見かけることがありますが、地名としての読み方は「きべ」が正式です。平仮名表記にしてくれたら…と願いたくなるような地名のひとつですね。
西吉部(宇部市)
「にしきべ」?それとも「にしよしべ」?
正解は「にしきべ」です!
「吉部(きべ)」の西側にある地域ということで、シンプルながら難読。吉部とセットで覚えるとスッキリしますね。こういった方向+地名の組み合わせパターンも、意外とひねった読み方になることが多いです。
秋穂(山口市)
秋の穂…そのまま「あきほ」?
いえ、「あいお」と読みます!
山口市南部に位置する海沿いの町で、美しい干潟と車えびの養殖が有名です。観光地としても知られており、読み方のギャップに驚く人が多い地名のひとつ。「あいお温泉」などの施設名でも見かけます。
阿知須(山口市)
「阿知須」、一瞬「おちす」と読んでしまいそう…
でもこれは「あじす」と読みます。
山口市西部に位置し、山口きらら博記念公園の所在地としても有名な地域です。読み方が「味噌(みそ)」に似ていることから、地元グルメと絡めたキャッチフレーズが使われることも。実は交通アクセスも良好な便利な地域です。
鋳銭司(山口市)
「鋳銭司」…これはかなり手ごわい!
正解は「すぜんじ」と読みます。
「鋳銭」は“貨幣を鋳造する”こと、「司」は“役所”。つまり、昔は貨幣鋳造に関係した役所があったことが由来です。山口市南部にあり、山陽新幹線の駅(新山口駅)にも近いエリア。地名が放つ歴史ロマンを感じられますね。
椿東(萩市)
「ちんとう」?「つばきひがし」?
実は「ちんとう」と読みます!
「椿」は「ちん」と読む別名があり、萩市椿東(ちんとう)は市街地の東側に広がる住宅エリアです。「椿西(ちんざい)」も存在するため、セットで覚えると便利。観光で訪れると必ず目にする地名なので、読み方は要チェック!
まとめ:山口県の難読地名は、奥深さの宝庫!
いかがでしたか?
山口県には「特牛」や「杢路子」など、見た目と読み方がまったく一致しない地名がたくさんあります。
こうした地名には、自然の地形、古語、産業、そして方言など、その地域ならではの背景が詰まっているんです。
地元の人には当たり前でも、外から来た人にとっては読めるだけで一目置かれるかも?
山口を旅する時や引っ越す予定がある方は、ぜひこの記事をブックマークして“難読地名マスター”になってくださいね!
関連記事